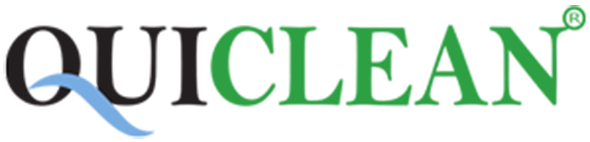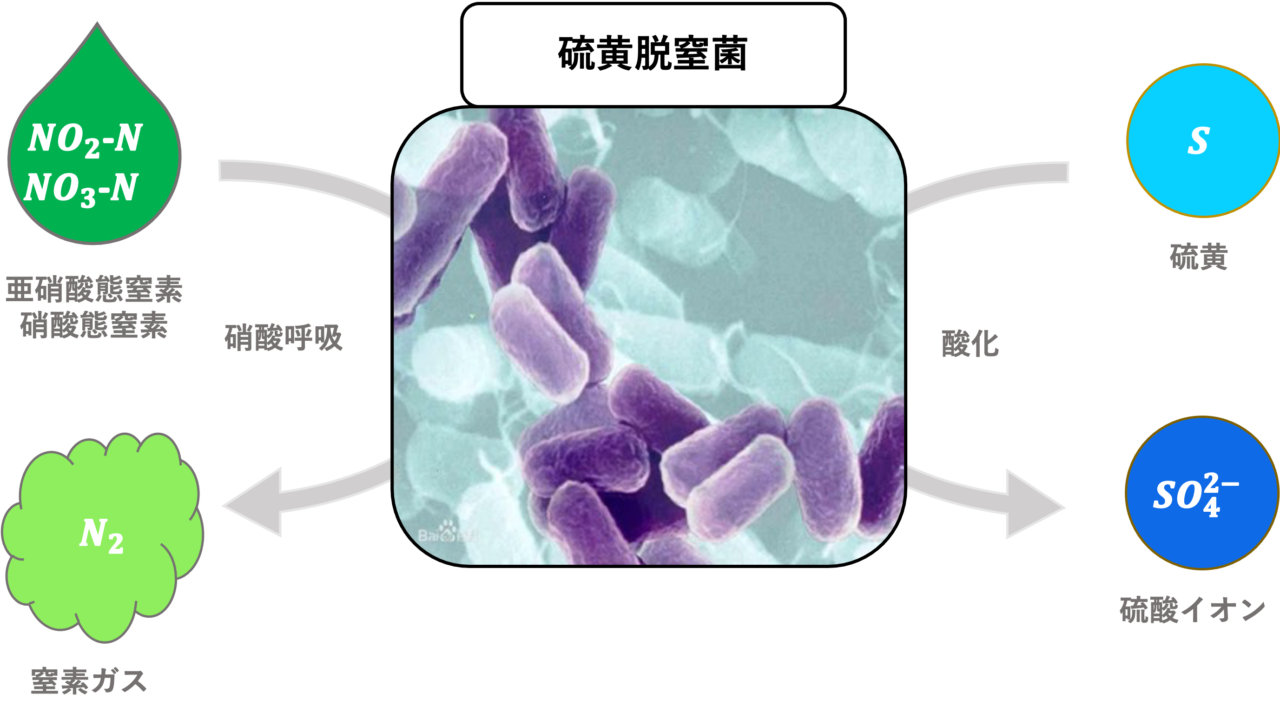【排水処理用語】硫黄酸化脱窒菌
目次
硫黄酸化脱窒菌とは
チオ硫酸塩、硫化物、元素硫黄といった硫黄化合物を酸化してエネルギーを得る微生物の総称。後述の「脱窒」能力を併せ持つため、排水中の窒素除去に利用される。
脱窒(だっちつ)とは
酸素が不足した状態(嫌気状態)で、微生物が酸素の代わりに硝酸塩(NO₃⁻)や亜硝酸塩(NO₂⁻)を呼吸(硝酸呼吸)に利用し、最終的に無害な窒素ガス(N₂)に還元する働きのこと。硫黄酸化脱窒菌は、このプロセスに必要なエネルギーを硫黄の酸化によって得る。
エネルギー獲得と脱窒のプロセス
S⁰
硫黄
NO₃⁻
硝酸塩
SO₄²⁻
硫酸イオン
N₂
窒素ガス
独立栄養性細菌(どくりつえいようせいさいきん)とは
増殖に必要な炭素源として、有機物(BOD成分など)ではなく、二酸化炭素(CO₂)などの無機炭素を利用できる細菌。硫黄酸化脱窒菌はこのタイプであるため、一般的な脱窒処理で必要となるメタノール等の有機物を添加する必要がない。これにより、コスト削減と管理の簡素化が可能となる。
まとめ:弊社の硫黄酸化脱窒技術
これまでの用語で解説した原理を応用したものが、弊社の排水処理ソリューションです。以下の特長により、効率的で経済的な窒素除去を実現します。
固体硫黄の直接利用
安価で取り扱いやすい固体の硫黄(S⁰)を担体に加工して、エネルギー源として利用します。
独自の複合菌株
特性の異なる複数の菌を組み合わせることで、様々な排水に対し安定した処理能力を発揮します。