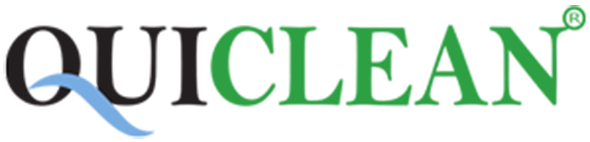排水中から窒素を処理することを、脱窒(だっちつ)といいます。このページでは、脱窒処理に関する基礎的な知識を共有します。
なぜ窒素を処理しなければいけないのか?
そもそも、皆さんはなぜ窒素を処理する必要があるのかご存知でしょうか?この説明で良く用いられるのが、赤潮とアオコと呼ばれる、窒素が原因で発生する自然現象です。
赤潮とアオコ


どちらの現象も、海や湖に窒素を多く含んだ水が流れ込むことで、植物プランクトンが急成長し、水面を覆ってしまう現象です。
窒素は、肥料に使われるなど、植物や野菜の成長には欠かせません。そのため、水中の窒素濃度が高まることで、植物プランクトンの急成長につながるのです。
赤潮やアオコが発生すると景観が悪化するだけではありません。植物プランクトンが水面を覆うことで、水中に日光が差し込まず、水中の植物は光合成ができなくなります。これにより、水中の溶存酸素濃度が低下し、一帯の魚が死滅し、悪臭や漁獲量の減少につながります。
このように、窒素を処理しないと、観光業や漁業などの産業に悪影響があるのです。
メトヘモグロビン血症
人間の健康にも悪影響があります。窒素は地下に浸透することで地下水汚染の原因になります。高濃度の窒素を含んだ井戸水を乳幼児が摂取すると、血中のヘモグロビンが酸素と結合するのを阻害されて、酸欠になるメトヘモグロビン血症(ブルーベビー症)という病気を発症します。原因となる硝酸態窒素は、揮発性がないので、煮沸しても効果はありません。
このように、窒素を処理しない悪影響というのは決して小さいものではありません。
排水中の窒素は4種類ある
排水中の窒素を処理する重要性をご理解いただいた所で、窒素の種類についてご説明します。窒素を処理すると言っても、排水中の窒素は1種類ではありません。窒素には4種類あります。

窒素の種類
有機窒素
有機窒素とは、タンパク質やアミノ酸由来の有機的な窒素です。排水中に固形で存在するものは、凝集処理で処理が可能です。
アンモニア態窒素
アンモニア態窒素は、アンモニウムイオン(NH4+)もしくは、アンモニア(NH3)の形で存在する窒素です。好気状態(溶存酸素が豊富な状態)で微生物により、硝酸態窒素や亜硝酸態窒素に変換されます。(硝化)
亜硝酸態窒素
亜硝酸態窒素は、亜硝酸イオン(NO2-)で存在する窒素です。先述したメトヘモグロビン血症の原因物質です。
硝酸態窒素
硝酸態窒素は、硝酸イオン(NO3-)で存在する窒素です。無酸素状態で微生物により、硝酸態窒素は窒素ガス(N2)に変換されます。(脱窒)
硝化と脱窒
排水中の窒素処理は2段階に分けて行われます。
硝化
アンモニア態窒素を亜硝酸態窒素、硝酸態窒素に変換する段階。硝化菌と呼ばれる、好気状態で働く微生物により行われます。硝化は、アンモニア態窒素を硝酸態窒素に変換するだけです。そのため、排水中の窒素は姿を変えただけで、窒素の総量は基本的には変わりません。
脱窒
亜硝酸態窒素と硝酸態窒素を、窒素ガスに変換する段階。脱窒菌と呼ばれる、無酸素状態で働く微生物により行われます。弊社の採用する硫黄酸化脱窒法もこの分野の技術です。脱窒することによって、初めて排水中から窒素の総量を減らすことができます。
日本と海外の放流基準
放流可能な窒素濃度は、環境省が水質汚濁防止法で定めています(環境省のページはこちら)。実は、日本は中国や韓国、東南アジアに比べて、環境の規制値が高く設定されています。
日本とアジア諸国の窒素の放流基準比較
日本の放流水全窒素濃度 : < 100 ppm
韓国の放流水全窒素濃度 : < 20~25 ppm
中国の放流水全窒素濃度 : < 5~15 ppm
フィリピン等の東南アジア : < 10~ 14 ppm
これには、日本の河川が他国よりも流れが急であり、自然の浄化力が高いなどの地理的条件も関係していると筆者は考えていますが、他国からの要求により、今後厳しくなる方向に向かう可能性もあります。
生物的脱窒
窒素を処理する方法として硝化と脱窒を見てきましたが、さらに脱窒方法について深掘りしたいと思います。脱窒方法には微生物の力を借りて行う、生物的脱窒処理と、イオン交換樹脂などを使用して行う、化学的な脱窒処理があります。ここでは生物的な脱窒処理を扱います。
従属栄養性脱窒と独立栄養性脱窒
生物的脱窒には、従属栄養性細菌を使用した従属栄養性脱窒と独立栄養性細菌を使用した独立栄養性脱窒の2種類があります。
従属栄養性細菌と独立栄養性細菌の違い
両者の違いは、生物が生きるのに必須な有機物が何の炭素源から作られるか?という違いです。従属栄養性細菌の炭素源が有機物、独立栄養性細菌の炭素源は二酸化炭素です。それでは、これによる脱窒処理の違いについて見ていきましょう。
従属栄養性脱窒
従属栄養性脱窒で活躍する従属栄養性細菌は、炭素源として有機物を利用します。そのため、排水中に有機物が必要なのです。
従属栄養性脱窒の場合には、排水中の脱窒を行う際の炭素(C): 窒素(N) :リン(P)の理想的な比率が C : N : P = 100 : 5 : 1と決まっています。つまり、窒素を5 kgの窒素を処理したい場合には、炭素100 kgとリン1 kgが必要ということです。
炭素源が足りない場合には、メタノールなどの有機炭素源を添加して補います。しかしこれは同時にBODを増加させます。そのため、再曝気槽を設置するなどの対策が必要になります。
メリット
- イニシャルコストが比較的安くて済む。
デメリット
- 継続的にメタノールの投入が必要となり、多額のランニングコストがかかる。
- 厳しい窒素の環境規制をクリアする際には、窒素とBODのシビアな運用管理が必要になるため、処理水質が不安定になり運用が難しい。
独立栄養性脱窒
独立栄養性脱窒で活躍する独立栄養性細菌は、炭素源として二酸化炭素を利用します。そのため、排水中に有機物がなくても問題ありません。(弊社の硫黄酸化脱窒菌もこの分類です。)
そのため、例えば、高窒素負荷かつCNP比が歪な嫌気消化液、そして無機排水などの工業排水などの処理に最適です。これらの排水を従属栄養性脱窒で処理する場合には、窒素負荷に対して炭素源が足りない為、メタノールなどの薬剤で補う必要があります。
しかし、硫黄酸化脱窒法をはじめとする独立栄養性脱窒であれば、薬剤は必要ありません。それにより、薬剤の補充や保管、添加量の調整などの煩雑な管理コストも無くなります。
メリット
- 薬剤のランニングコストがかからない。
- 厳しい環境規制に対して安定的な処理が可能になる。